- 「くもんの小学ドリル 2年生・たし算」ってどんな内容?
- 実際に使ってみて感じた良いところ・注意点は?
- 年長でも“たし算の筆算”はできる?
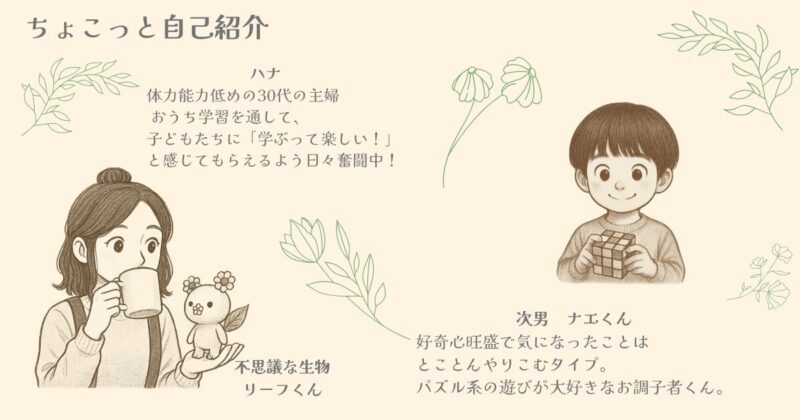
年長だけど「くもんの小学ドリル2年生・たし算」に挑戦しました!
我が家の次男ナエくん(現在年長)は、2~3歳ごろからドリルが大好き✨
自然と先取り学習をするようになり、今では小学生の内容に取り組んでいます。
算数は、年中のときに1年生の範囲を終えたので、年長では2年生の内容にチャレンジ中。
学年に合わせた順番で、「たし算の筆算」→「ひき算の筆算」→「かけ算」…という流れで進めていく予定です。
 ハナ
ハナ2年生の算数には「表とグラフ」「長さの単位」「水のかさ」などの単元もあるけど、まずはナエくんが取り組みやすそうな計算の単元からスタートしてみたよ😊
ということで、最初に選んだのは、「くもんの小学ドリル 2年生 たし算」。
今回は実際に使ってみた感想や、注意点をレビューします。
年長での先取り学習や、くもんの2年生ドリルが気になっている方の参考になればうれしいです!
くもんの小学ドリル2年生・たし算ってどんなドリル?
- ドリル名
くもんの小学ドリル 2年生たし算 - 発行所
株式会社くもん出版 - 価格
680円+税10% - レベル感
小学2年の基礎力をつけたい方向け - 中身の構成
全95ページ(うち問題ページは84ページまで)・42回分・カラー
小学2年生で学ぶ、いろいろなタイプのたし算が解ける!
このドリルには、たし算の筆算だけでなく、2年生の算数で学習するさまざまな種類のたし算がバランスよく掲載されています。
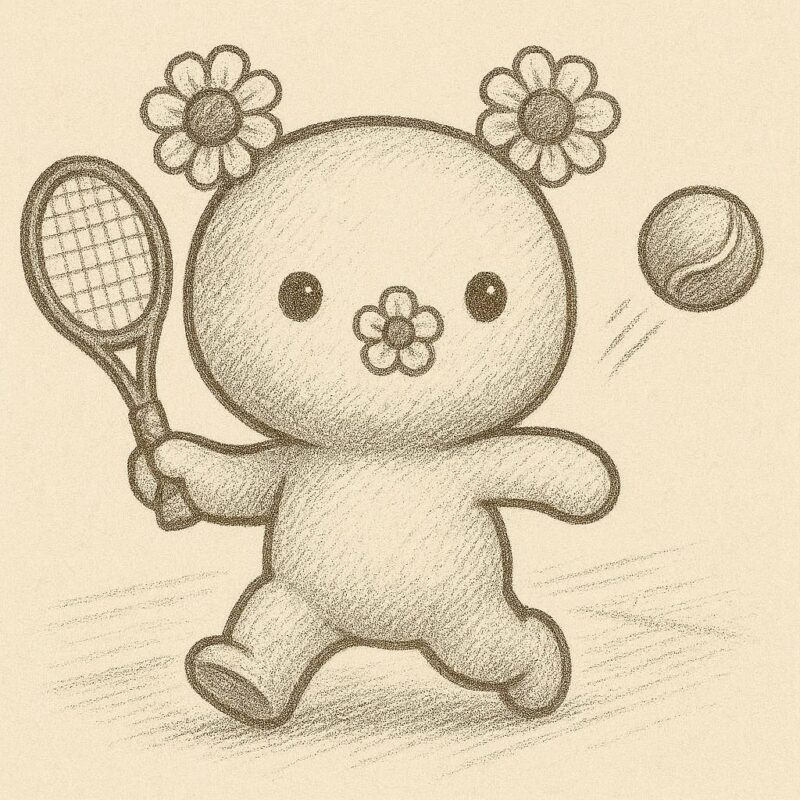
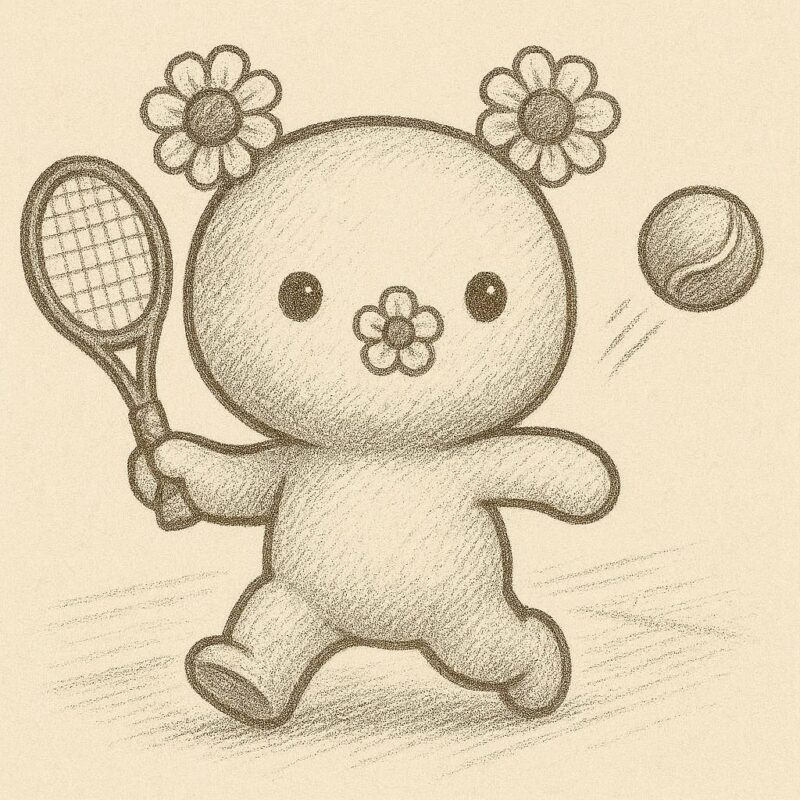
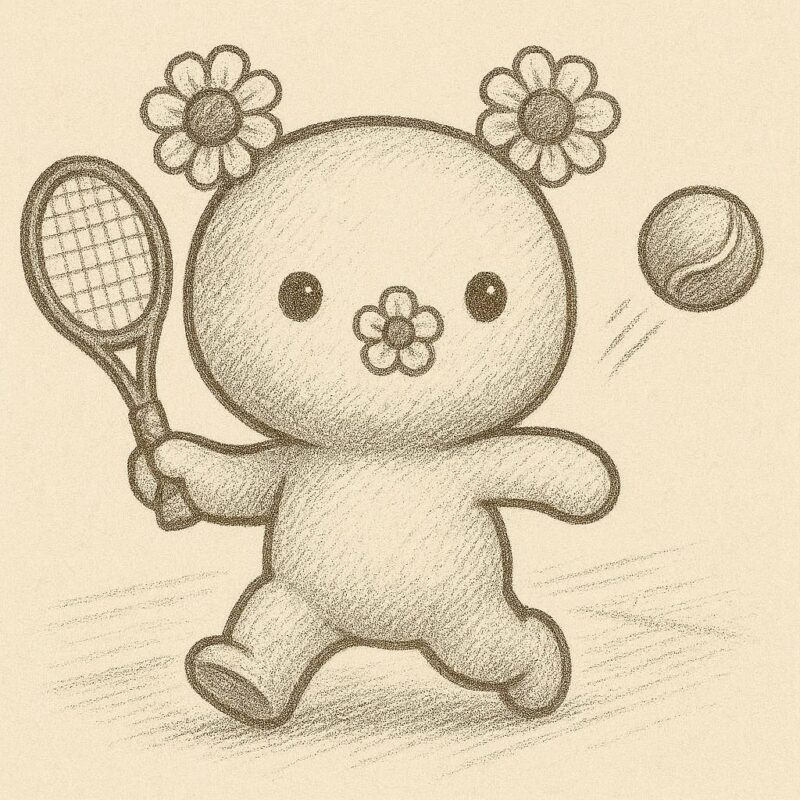
2桁の筆算
3桁の筆算
大きな数のたし算
工夫して解くたし算
2年生のたし算を集めたドリルなのだ!
2年生のたし算にしっかり特化した構成になっていて、「たし算を得意にしたい!」という子にぴったりです。
難易度としては、基礎がわかっていればスムーズに解けるレベル。
教科書内容にそった問題が中心で、ひたすら練習できるページ構成です。
基礎中心ですが、発展的な問題も少しだけ含まれています。
1枚ずつ切り取って使えるから、量の調整もしやすい
このドリルは全42回分。1枚ずつ切り離して学習できるつくりになっています。
切り離すことで「今日はこの1枚だけ!」と学習量が見える化されるので、子どもにとっても取り組みやすいようです。



やる気アップにつながるね!
1枚あたり、片面に20~25問ほど。両面で取り組むと、40~50問になります。
子どもの集中力や気分にあわせて「今日は1枚だけ」「やる気がある日は2枚」といった調整がしやすいのも魅力。
文字サイズも小さすぎず、1問ごとの間にスペースがしっかりあるので、まだ小さな字が書きにくい年長さんでも安心して取り組めます。
50年以上の実績!公文式教材の考え方が活かされたドリル
このドリルは、公文式の教材で長年培われた「子どもの理解に寄り添う学び方」がもとになっています。
内容は、子どもが無理なくステップアップできるように構成されていて、少しずつレベルアップしながら、同じタイプの問題を繰り返し解く仕組みになっています。
繰り返し学習によって、計算力や理解がしっかりと定着するよう工夫されているのが特長です。



私が子どもの頃も、「くもんに通ってる子=頭がいい子」ってイメージだったので、くもんのドリルって聞くだけで信頼感がある!
このお値段で“公文式の学び”にふれられるのは、ほんとありがたい!
くもんドリル、ここが好きだった!!ポイント


見やすさと可愛さのバランスが◎
このドリル、個人的にとても気に入っているのが「見やすさと可愛さのバランスが良いところ」。
全体的にはシンプルでスッキリしたデザイン。カラー印刷ではあるものの、派手すぎず控えめなので、学習中に気が散りにくい印象です。
問題の合間には、さりげない可愛らしいイラストがアクセントとして入っていて、「楽しそうかも?」と子どもが感じやすい工夫もされています。
問題数はしっかりありますが、ページ全体がごちゃごちゃしておらず、圧迫感を感じさせないデザイン。
ドリルによってはイラストが多すぎて、逆に集中が続かないものもありますが、このドリルは「取り組みやすさ」と「ちょうどいい可愛さ」が共存していて、とても好印象でした。
表紙裏のアドバイスが参考になった!
ドリルの表紙裏に書かれていた「くもんのドリルの上手な使い方」がとても参考になりました。
特に印象に残ったのが「マルつけの仕方」についてのアドバイスです。
かならず「100点」にしましょう。
採点するときには、まちがった問題にだけ小さくチェックをつけて、
その場で直すくせをつけましょう。
すべて直したら、花丸や「100点」をかきましょう。
これを読んで、「そうすればよかったのか!」と目からウロコ。



今までのマルつけ、ちょっともったいなかったかも?
私は今まで、1問ずつマルやバツをつけて採点していたのですが、
それだと、せっかく頑張って解いたページがごちゃごちゃして見えるのが少し気になっていたんです。
でもこの方法なら、間違いは最小限のチェックだけ。
直したあとに、きれいな花丸や100点で達成感を演出できる!
見た目もスッキリして、子どもも気持ちよく「やりきった感」を味わえそうだなと思いました。
さっそく次のマルつけから、試してみようと思います!



ドリルやテキストにかならず書かれている「ドリルの使い方」や「おうちのかたへ」のページは、実は見逃せない宝の山!
ついつい読み飛ばしていたけれど、今回は「読んでみてよかった!」と思える内容でした。
次からは、ちゃんと目を通してみようと思います😊
くもんのドリルを使っている方は、ぜひ表紙の裏ページもチェックしてみてくださいね!
小2用のくもんドリルを年長で使うときの注意点


解説がない!“ドリル”ならではの特性
このドリルはあくまで“ドリル”なので、新しい単元の学習ポイントや解き方の詳しい解説は載っていません。
たとえば、「引き算の筆算のやり方はこう!」といった手順の説明は省かれています。
我が家の場合は、筆算の仕組みについては私が簡単に説明してあげることができたので、問題なく進められました。
最初にやり方を理解できていれば、そのあとはどんどん問題に取り組める構成です。
「手順の説明からしっかり載っていてほしい」という方には向かないかもしれませんが、
「手順は私が教えるから大丈夫!」という親御さんや、
「やり方はもうわかっているから、とにかく練習量をこなしたい!」というお子さんにはぴったりです。
幼稚園児には1日1枚でも負担になることも
このドリルは小学校2年生向けに作られているので、年長さんが取り組むには少し学習量が多めです。
特に筆算のようにステップを踏んで考える問題では、1枚全部やるのがしんどい日もあります。
簡単な内容の日は、2~3枚とスイスイ進むこともありますが、
難易度が上がると片面だけでも「もう疲れた…」という様子になることも。
そんなときは「じゃあ今日は片面だけでOK」と、柔軟に対応しています。



幼児期の学習で大事なのは「無理をさせないこと」が大切なのだ✨
疲れたときは無理にやらせず、でも「やりかけで終わらせないように、片面はやりきろうね」と声をかけ、“やりきる感覚”を大事にしています。
無理をしないことで、やる気が続きやすく、子どもも前向きに学習を進めることができるので、
こうした柔軟な対応が大切だと感じています。
小2用のドリルを年長で使うには、いくつか注意点はありますが、
親がしっかりサポートできる環境であれば、十分に活用できます。
無理せず、お子さんのペースに合わせて進めていくことが大切です。
実際のところ…年長で「たし算の筆算」ってできたの?


結論から言うと…しっかりマスターできました!
我が家のナエくんは、これまで小学校の学習順にそって進めてきたので、
「わからない!」と戸惑うことなく、筆算のルールもすんなり理解することができました。
今回取り組んだ『くもんの小学ドリル 2年生 たし算』も、
いきなり筆算に入るわけではなく、最初は1年生の復習のようなウォーミングアップ問題からスタート。
なじみのある問題から少しずつ難しくなっていく構成なので、
「急に難しくなってびっくり!」ということはありませんでした。
理解はOK!でも、書く部分にはちょっと課題も
もちろん、年長さんならではのつまずきポイントもありました。
たとえば…
- 桁をそろえて書くのがまだ難しく、数字がずれてしまう
- 繰り上がりの数字が大きく書きすぎて、答えとまざってしまう
などなど、「筆算のやり方」は理解できていても、見た目の整え方や数字のバランスには課題が残りました。
でもこれは、まだ小さい子どもだからこそ自然なこと。
焦らず、少しずつ「丁寧に書くこと」も身につけていけばいいかなと思っています。
結論:段階的に進めていけば、年長でも筆算はバッチリ理解できる!
学年にとらわれすぎず、今の子どもにちょうどいい内容から段階的に進めることが大切だと改めて実感しました。
「年長でも筆算できるかな?」と気になっている方も、ぜひお子さんのペースに合わせて挑戦してみてください!



「くもんの小学ドリル2年生・たし算」に取り組んだのは
年中の3月~年長の6月の期間だったのだ✏️
次は「ひき算のひっ算」に挑戦なのだ😊
今回の記事のポイント&ハナのひとりごと
今回の記事のポイントはここ!
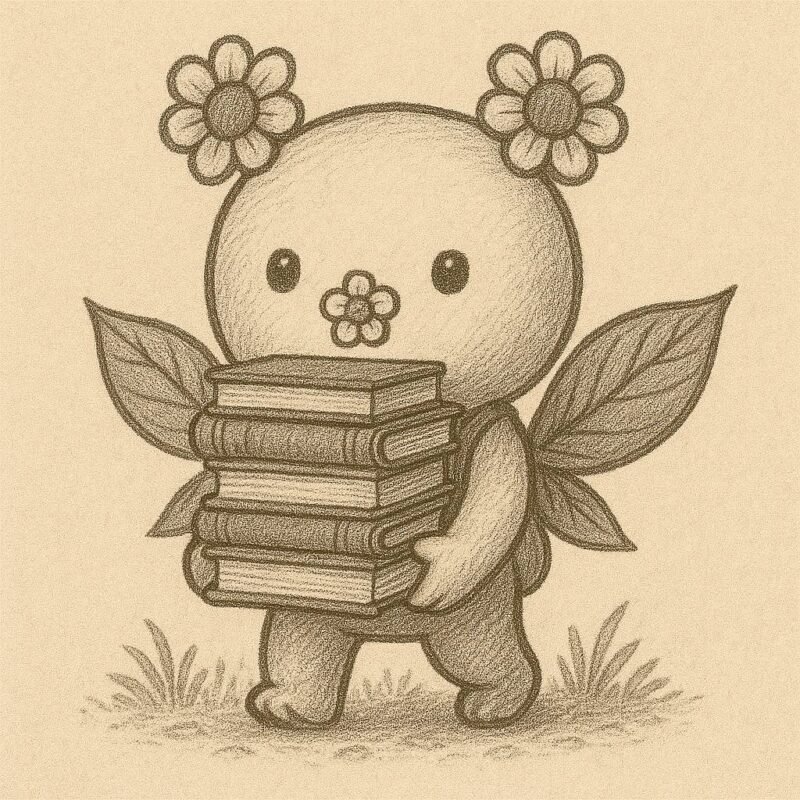
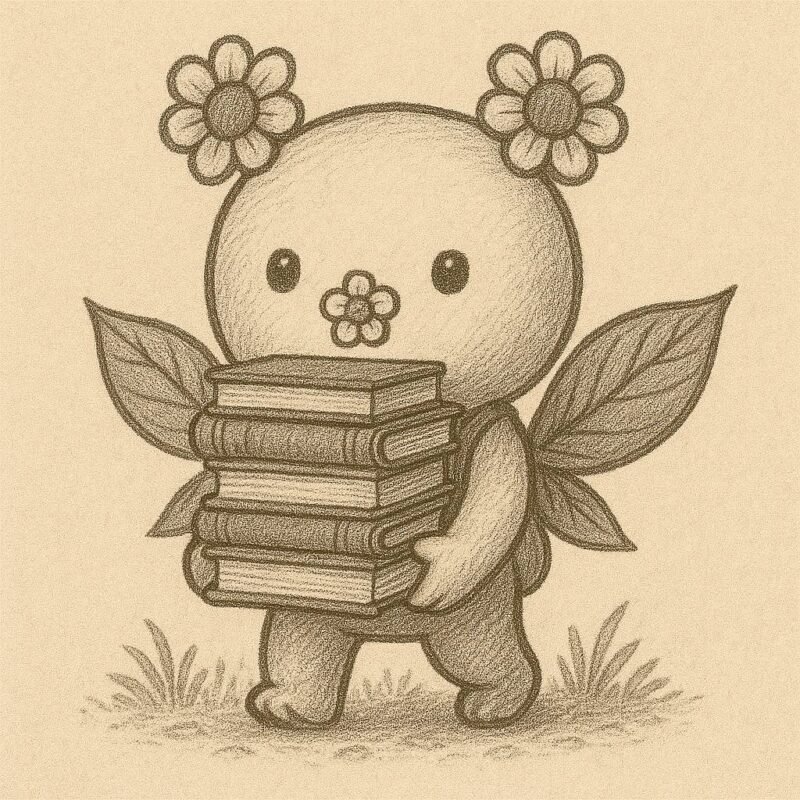
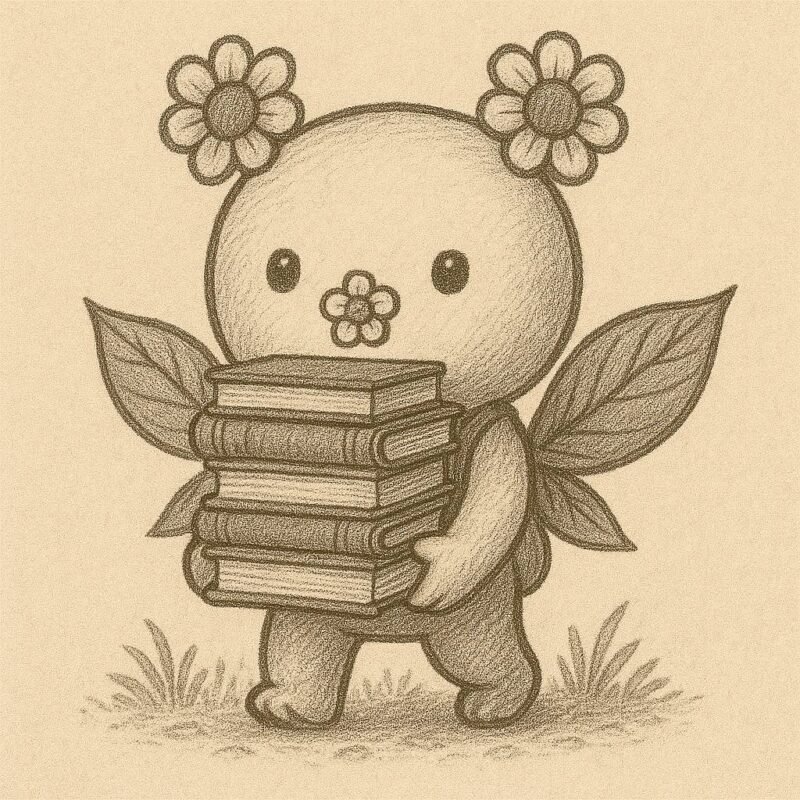
今回はこんな内容だったのだ!
「くもんの小学ドリル 2年生・たし算」ってどんな内容?
このドリルには、小学2年生で学ぶさまざまなたし算がバランスよく掲載されています。
- 2桁の筆算
- 3桁の筆算
- 大きな数のたし算
- 工夫して解くたし算
難易度は、基礎が身についていればスムーズに解けるレベル。
50年以上の実績がある公文式の学習法をもとに、無理なくステップアップできる構成になっており、子どものやる気を引き出す工夫がされています。
実際に使ってみて感じた良いところ・注意点は?
見やすさと可愛さのバランスが良く、ページ全体がすっきりしていて圧迫感がありません。
気が散りにくく、子どもも集中しやすいデザインです。
また、表紙裏にある親向けのアドバイスも意外と参考になるので、一度目を通しておくのがおすすめ。
ただしこの教材は“ドリル”なので、新しい単元の詳しい説明はなく、先取りで使う場合は親がやり方を教えてあげる必要があります。
小2向けの内容なので、年長さんには1日1枚にこだわらず、無理のない量で進めるのが大切です。
年長でも“たし算の筆算”はできる?
段階的に進めれば、年長でもたし算の筆算を理解することは可能です。
『くもんの小学ドリル 2年生 たし算』は、いきなり筆算に入るのではなく、最初は1年生内容の復習からスタートし、少しずつステップアップしていく構成。筆算に入る頃には、自然と考え方の土台ができていました。
もちろん、年齢的にまだ
- 桁をそろえて書くのが難しい
- 繰り上がりの数字が大きくなりすぎて答えと混ざってしまう
といった書き方の課題はありますが、理解自体はしっかりできており、書き方は今後の成長で少しずつ身についていくと感じました。
ハナのひとりごと
なんとなく…の話なんですが、私は今まで「くもん」のドリルを選ぶのを避けてきました。
なぜかというと、「くもんっていいよ!!」みたいな話しか聞かないから。
そう言われれば言われるほど、逆にちょっと反抗したくなるというか…
「いやいや、他にもいい教材あるから!信者にはならないから私!」っていう気持ちになってたんです。
でも、次男の学習でふと手に取ったくもんのドリル。
実際に使ってみた私の感想はというと…
「くもんって……いいじゃん!」
(なんとなくで避けててごめんなさい、くもんさん)
色々なドリルを試してきましたが、やっぱりくもんのドリルには独特の工夫があるなと感じました。
「どうすれば子どもがスムーズに学べるか?」がちゃんと考えられている作りで、
学習塾としての経験とノウハウが教材にも反映されているんだなと、しみじみ実感。
今後も我が家はきっとお世話になると思います。



くもんのドリル、認めざるを得ません。おすすめです!
(まわし者じゃないです!ほんとに!)
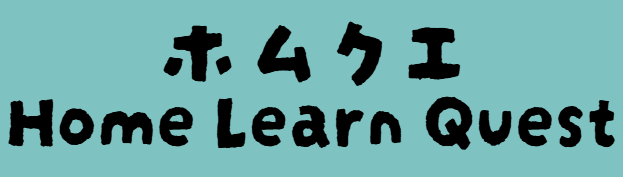


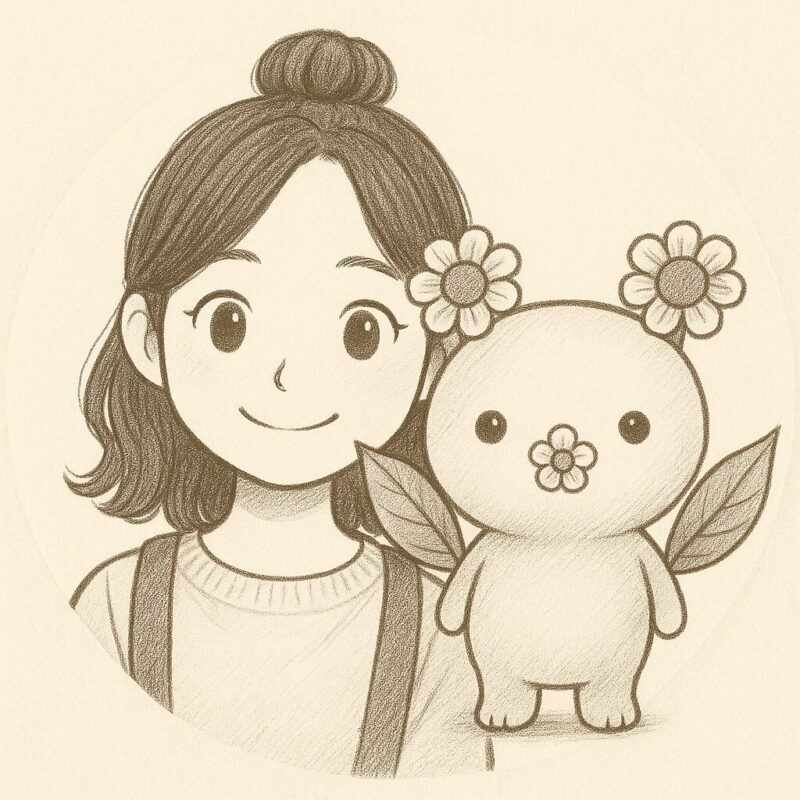


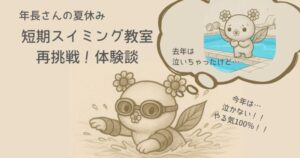

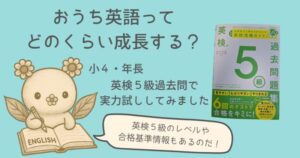

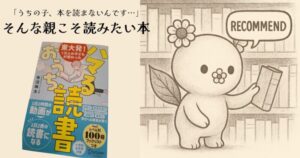

コメント